ある日、息子が学校から帰宅すると、
いつになく真剣な瞳で
「学校をやめさせてほしい」
その言葉が耳に届いても、
まずは「???」
次に浮かんだのは
「小学校ってやめられるっけ?」
という疑問。
言葉の意味をそのまま解釈するのが精一杯。
ただ立ち尽くし、
息子の表情を見つめ返すことしかできない。

私は小学生の息子と娘を育てる母です。
息子は、グレーゾーンの5年生で
支援学級に在籍していますが、
今はほとんど学校に行けていません。
娘は、軽度知的の3年生で、
こちらも2年生の3学期から
学校渋りが始まり、
全く登校できていません。
息子は、小学校に入って2ヶ月ほどで
同級生とのトラブルで不登校に。
それから、
ずっと再登校と不登校を繰り返しています。

当時の私は
「母親として私が何とかしなきゃ」
と強く思い込み、
必死で解決策を探していました。
不登校になり始めた頃は、
「1年生のこんな早い時期から
つまずくなんて……
将来どうなるんだろう……」
それが率直な想いでした。

同じ部屋にいても、
リビングに流れるのは
YouTubeの音だけ。
「お昼ごはんどうする?」
と声をかけても、返事はない。
当時、口にすることといえば、
「死にたい」
「なぜ生きていかないといけないの?」
と「死」を連想させるような言葉ばかり。
夜になると、子どもの将来と
今までとは違う息子の様子に泣き続ける。
そんな夜を長い間過ごしていました。

きっかけが
同級生とのトラブルだったこともあり、
「人とうまく関われるようになれば、
また学校に行けるはず」
そう信じて、育児書や発達関連の本を
片っ端から読み漁りました。
ページをめくるたびに、
「これならうまくいくかもしれない」
と淡い期待を抱き、
書かれていることをいろいろ試してみる。
でも、心の中から焦りは消えません。
「このままでは将来、
社会に出て
働くことさえ難しくなるかもしれない」
そんな不安に追われながら、
答えを探し続けていました。

けれど、
どれだけ本に書かれていることを試しても、
思うような結果は出ません。
あなたもどこかで聞いたり、
目にしたりしたことは
あるんではないでしょうか?
「家の居心地が良いから学校に行かない」
という言葉。
私は、この言葉を鵜呑みにして、
学校と同じ時間割のような生活を
家庭で再現してみたこともあります。
あとは、
「ゲームとYouTubeずっとやってる問題」
本当に、ずっと1日中。
どこにも行かず、勉強もまったくせず、
テレビを占領されることにも、
見たくもない動画ばかり見せられるのも
うんざりしてしまいました。

それに、世間は
「スマホやゲームには制限を設けましょう」
が一般的な考え。
学校からも、
「今日はどんなふうに
過ごしていましたか?」
なんて聞かれることもしばしばです。
「今日も1日中ゲームをしていました……」
そう答える度に、
子どもの相手もしない親。
とレッテルを貼られているような気分でした。

世間体も気になる。
先生たちにもっと違う報告をしたい。
そう強く感じた私はついに
「1日2時間まで」
と制限をかけて、
とにかく私の不安や
世間に対する後ろめたさを拭うことばかり。
当然のことながら、これらの行動は、
息子にとって重荷にしかなりません。
気づけば私は、息子のさらなるストレスや
追い詰めになっていることにも気づかず、
本やインターネットばかりに頼り、
目の前の息子を見ている
“つもり”になっていました。

「こうすればうまくいく」
と信じて試しても、すべてが空回り。
努力すればするほど、
私はどんどん疲れていき、
子どもとの心の距離は開いていく。
子どもの笑顔は
ほとんど見る機会がなくなり、
どんどん話もしてくれなくなる。
そして、なに1つうまくできない自分を
責める気持ちばかりが
膨らんでいったのです。

そんな日々の中、息子の定期通院で、
いつものように
主治医のもとを訪れました。
診察の最後に
「学校生活はどうですか?」と聞かれ、
思い切って打ち明けてみました。
「実は、今は学校に行けていないんです」
先生はゆっくり振り向き、
少し天井を仰いでから、
「みんなに合わせて学校に行くことが、
必ずしも息子くんに合うとは限りませんよ」
「一般的にはこうした方がいい
と言われていることがありますが、
息子くんに合うかどうか
やってみないとわかりませんよね」
穏やかな口調で言われ
私はハッとしました。

それまで私は
“学校に行かせること”
ばかりにとらわれていました。
「どうすれば行けるか」
「なぜ行けないのか」ばかりを追いかけ、
目の前の息子の心を見失っていたのです。
主治医の言葉は、
私の考え方に
大きな風穴を開けてくれました。
学校に行けるかどうかではなく、
息子にとって
安心できる時間をどう作るか。
そこに目を向けるきっかけになったのです。
主治医の言葉を受けて、
私はこれまでのやり方を
少し手放してみることにしました。

登校するかしないか、何時から行くか。
それを息子自身に
決めてもらうようにしたのです。
学校の先生にも、考えを伝え、
少しだけ距離を取っていただきました。
同時に、「学校」や「勉強」のことは
いったん脇に置いて、
ただ一緒に過ごす時間を意識しました。
ゲームの話を聞いたり、
できそうなら、一緒にしてみたり。
同じ動画を一緒に見て、
いろいろ話をしてみる。
ほんの少しのことでしたが、
それは今までの私には
できていなかったことでした。
するとある朝、
息子が小さく笑ったのです。

その笑顔は一瞬でしたが、
私には眩しく映りました。
「よかった。
まだ生きることを
本気で諦めているわけではない」
そう思える、久しぶりの瞬間です。
それから私は、
「学校」や「勉強」のことを
口にすることをやめました。
もちろん、ゲームやYouTubeの制限も。
ただ、目の前の子どもたちと
「今を楽しむ」ことに集中したのです。

すると、
少しずつ息子の笑顔が増えていく。
ゲーム実況動画の話で一緒に笑ったり、
料理を並んで作ったり。
ほんの短い時間でも
「楽しい」と思える瞬間が
積み重なっていきました。
私自身も肩の力が抜けて、
息子との会話を自然に
楽しめるようになっていく。
「何をして過ごすか」
よりも
「一緒に安心できる時間を持つこと」
が、こんなにも心を和らげてくれるのかと
実感しました。
そうして親子の間に
温かな空気が流れるようになった頃、
息子は自然と少しずつ
学校に関心をもち始めました。
「明日……
給食だけ食べに行ってこようかな。
先生それでもいいって言ってたよね?」と。

私が無理に促したわけでも、
特別な指導をしたわけでもありません。
日々の小さな積み重ねが、
息子の心を
少しずつ前に動かしていったのです。
その変化を、
私はただ隣で見守っていました。
小さな成功を重ねるうちに、
私はあることに気づきました。
「学校に行かせること」
ではなく、
「親子で安心して過ごせる時間を持つこと」
それこそが、
一見遠回りに見えても
“再建”の近道になるのだと。
学校に行くか行かないかよりも、
まずは息子の
心が元気でいられることを優先する。

その上で、今何ができるか?
勉強よりも
生きていくための
スキルを身につけることの方が
よっぽど大切。
そう考えるようになりました。
その軸を持てるようになってから、
私は余計な不安に
振り回されなくなりました。
「みんなと同じように」
ではなく、
「わが家に合ったやり方で」
そう考えられるようになったとき、
ようやく親子の暮らしに
安心が戻ってきました。

これが、
わが家なりの
“スタイル”になっていったのです。
今、目の前の子どもが
学校に行けなくて悩んでいるあなたへ。
あなたの不安や焦りは、
とてもよくわかります。
でも、無理に登校させなくても大丈夫。
まずは「一緒に安心できる時間」を
少しずつ積み重ねてみてください。
むしろ、無理に登校させることは
親子の心の距離を開き、
自分の殻にこもってしまいます。

そうなると、
子どもの現在の状態を
確認することも難しくなります。
ただでさえ、
心の調子というのは
人にはわかりにくいもの。
それは、わが子でも同じ。
ほんの短い会話や、
同じ動画を眺めるひとときでも構いません。
その時間が、
子どもにとって
「ここにいていいんだ」
という安心につながります。

そして、小さな笑顔が戻ったとき、
きっとあなた自身の心も軽くなるはずです。
子どもと親、どちらの心も守ること。
それが、再建への何よりの第一歩です。

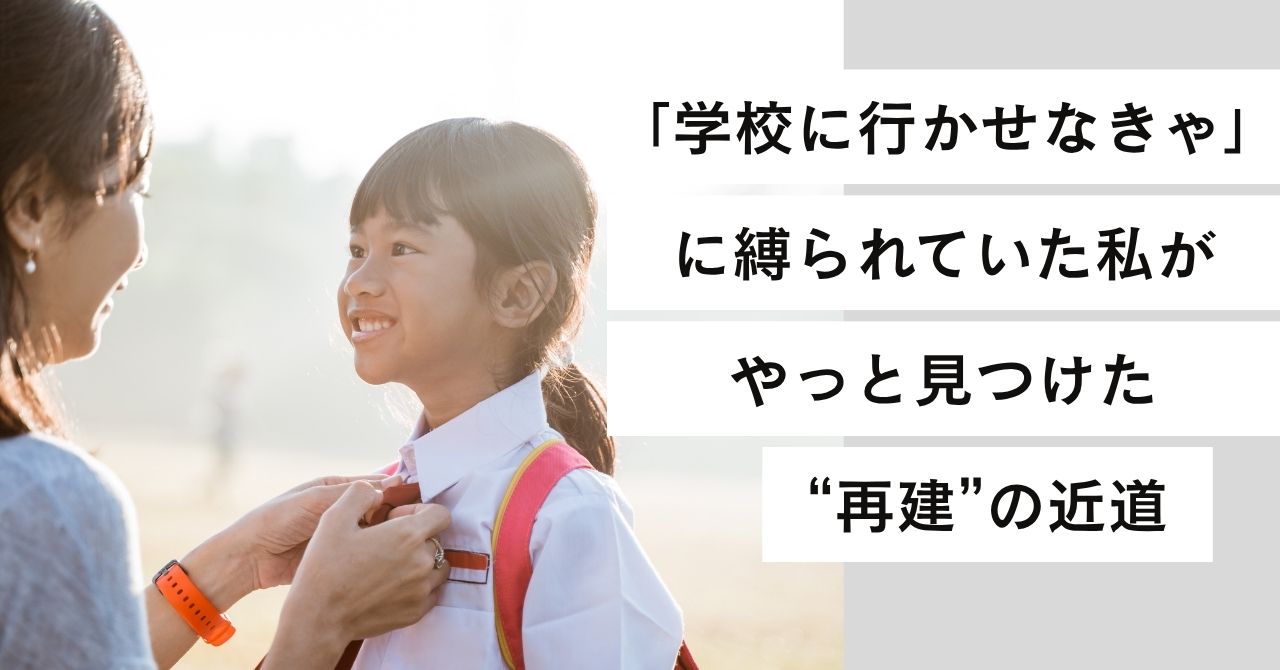

コメント